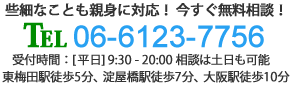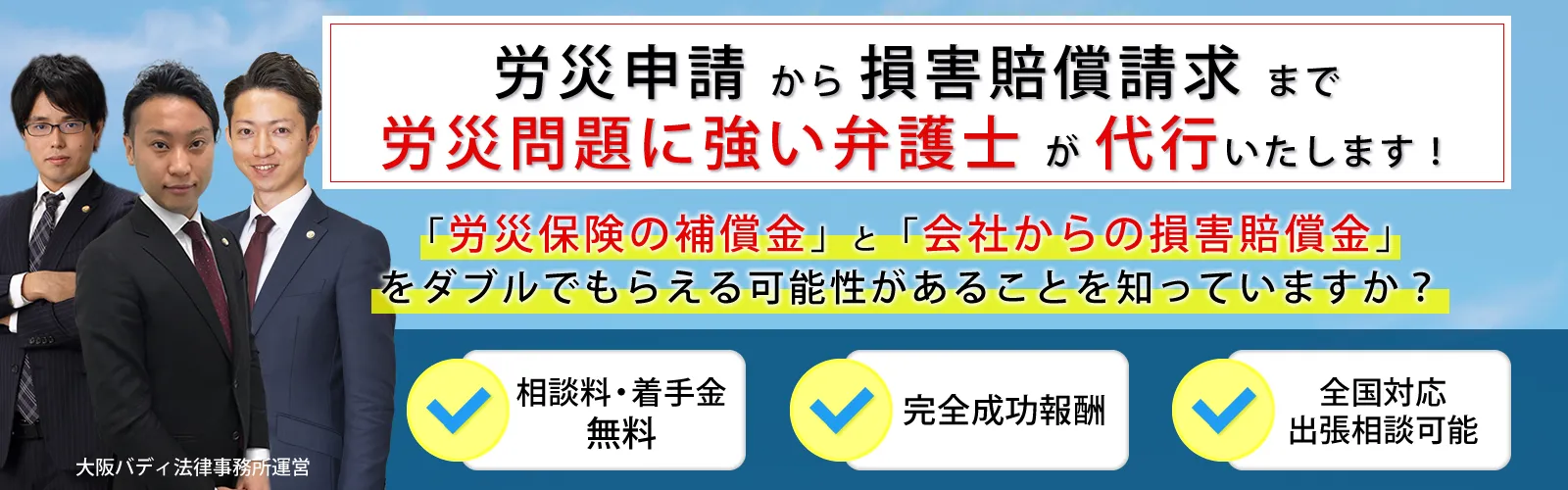事業者は、労働者に対し、労働災害を防止するために、ヘルメットや安全帯などの保護具を支給し、着用させることが義務づけられています。
今回は、足先の怪我や転倒を防止する「安全靴」に関し、その役割と事業者の責任を説明します。
日本工業規格(JIS)によれば「主として着用者のつま先を先しんによって防護し、滑り止めを備える靴」と定義されていることから、安全靴とは、着用者の足の保護と滑り止めの機能が具備された靴といえます。
このような安全靴は、主に工事現場や重量物を扱う工場内での作業で使用されています。
もっとも、安全靴の使用は工事現場などだけに限定されるものではありません。
労働者の作業環境に関する最低限の規制を定めた労働安全衛生法の同規則558条1項では「事業者は、作業中の労働者に、通路等の構造又は当該作業の状況に応じて、安全靴その他適当な履物を定め、当該履物を使用させなければならない」と規定しています。
同規則の文言が「通路等の構造又は当該作業の状況に応じて」と規定されていることからも、事業者には、労働者が行う具体的な作業内容が労働者の足先に危険が生じる場合や滑りやすい作業であるような場合には安全靴の着用させる義務があるといえます。
そして、この場合、事業者には安全靴を支給し、着用させることまでが義務付けられています。
安全靴を着用させるべき作業としては、工事現場全や重量物を扱う作業全般です。
また、重量物に限らず、運搬作業でも安全靴の着用が求められる場合があります。
なぜなら、材料などを倉庫などから運搬する際には、手押し台車(パレット)やかご台車を利用しますが、通常、作業効率を上げるため、このような台車に材料をいっぱいに積みこみます。
そうすると、材料一つ一つは重量物とはいえなくても、材料をいっぱいに積んだ台車の重量は200キロを超えることが多く、ちょっとしたはずみで意図しない方向に台車が動き、作業者の足のつま先などに台車の車輪が乗り上げることも珍しくありません。
もし、200キロもの重量物を支える車輪が足先などに乗り上げた場合、安全靴を履いていなければ骨折を免れませんので、運搬作業においてはその具体的な状況に応じて、安全靴の着用が必要といえます。
安全靴の着用の有無が問題となるよくあるケースとしては以下のようなものがあります。
作業者は、トラックで運ばれてきたかご台車を倉庫に運ぶ倉庫内作業に従事していたところ、倉庫に続く作業用通路が穏やかなくだりになっていたため、思ったよりも勢いが強く、かご台車を止めきれずに車輪が足に乗り上げて、足の指を骨折してしまう労働災害に被災した。
この倉庫内作業に関し、会社から安全靴は支給されていなかった。
かご台車の重量は、様々であったが重いもので200キロを超える場合があった。
かご台車の操作を誤ったのは労働者自身であり、労働者の不注意によって労災事故が生じているのだから、労災補償金とは別に、会社に損害賠償責任はない。
この場合、会社は、作業者に対し、安全靴を支給しなかったことに対する安全配慮義務違反が認められると考えられます。
まずは、今回の倉庫内作業が安全靴を支給すべき作業であったどうかが問題となりますが、200キロを超えることもある重量物を台車で運搬する作業ですので、台車の車輪が足先に乗り上げると非常に危険なことは容易に想定できます。
そして、作業通路は緩やかなくだりになっていることから、台車がうまく制御できず、作業者と接触することも容易に想定できるといえます。
このような作業内容と作業環境からすれば、事業者としては運搬作業中の労働者の危険を十分予期できるといえ、その危険から労働者を守るために最低限の保護具として安全靴を支給し、かご台車が足先に乗り上げても重傷に至らないように配慮する義務があったといえるでしょう。
したがって、この場合、安全靴を支給されずに労働災害に被災した作業者は、会社に対し、労災補償金とは別に、損害賠償請求を行うことができると考えられます。
労働災害が発生した際には、そもそも作業にあたって十分な保護具が支給されていたかどうかを検討してください。労働災害によっては、会社が十分な配慮を行い、安全靴などの保護具を支給していれば防げた事故が少なからずあります。
そして、安全靴などの保護具が必要であったかどうかの判断は重要ですので、もし、ご自身やご家族の労働災害で疑問に思うことがあれば、弁護士等の専門家に相談されることをおススメします。